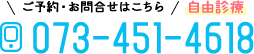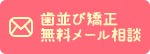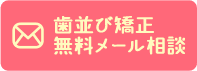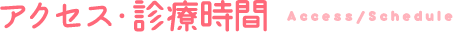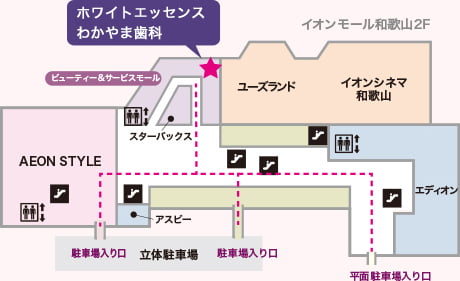悪い歯並びにも様々なタイプがあります

心配な場合は、一度歯科医師による診断を受けておくと安心です。当院では無料で矯正相談・検査・診断を実施していますので、是非お気軽にお越し下さい。
出っ歯(上顎前突)

原因と治療法
幼少期の唇を噛む癖や、舌で歯を前方に押し出すような癖が原因で、歯と顎の骨が変形してしまうことがあります。また、生まれつきの骨の形もありますので、上顎前突の場合は奥歯を軸に歯列を後方に移動させ、下顎が引っ込んでいる場合は前方に成長させて上下顎のバランスを整えます。症例を見る
叢生(乱ぐい歯、八重歯)

原因と治療法
顎に対して歯が大きかったり、顎自体が小さく歯列幅が狭いと、歯が生えるスペースが足りずに本来とは異なる場所から歯が生えてきてしまいます。成長期の子どもの場合は歯列幅を広げてきれいに歯を並べることができますが、年齢や症状によっては永久歯を抜歯して歯列を整える方法を採るケースもあります。症例を見る
受け口(反対咬合、下顎前突)

原因と治療法
出っ歯の治療とは逆に、受け口の治療では上顎骨の成長促進や下顎骨の成長方向の修正、歯の傾斜角度の調整を行います。遺伝で受け口になることもあれば、指しゃぶりなどの悪癖がいつまでも治らなかったために、下顎が前方に押し出されたケースもあります。
すきっ歯

原因と治療法
すきっ歯の原因には、顎の大きさと歯の大きさのバランス関係によるものや、もともと歯の数が少ない、子どもの頃に舌を歯の間に入れる癖があった等が挙げられます。乳歯列期のすきっ歯は、永久歯に生え変わる時のための必要な隙間ですので、自然と治ることも多いです。その場合は経過観察を行い、様子を見ながら矯正をするかを判断します。治療を行う場合は、隙間の大きさに合わせてマウスピース矯正かワイヤー矯正を行います。症例を見る
開咬

原因と治療法
開咬は、幼少期の歯の間から舌を出す癖や口呼吸などが原因であると考えられます。矯正治療で歯の傾きや咬合の高さを調整するほか、正しく舌を動かすトレーニングや、お口の中で舌が収まるポジションを修正します。舌の位置が低いと、矯正しても歯並びが元に戻ってしまいますので、専用の装置を使用して舌癖を改善します。症例を見る
過蓋咬合(噛み合わせが深い)

原因と治療法
歯列の拡大、下顎の成長促進によって、後方に押し込まれた下顎を適切な位置に移動します。一般的に上顎の成長の後に下顎の成長が始まりますので、小さなお子様の場合はすぐに矯正を行わず、経過観察を通して噛み合わせの変化をチェックします。過蓋咬合の原因としては、顎関節や骨格の成長のアンバランスによるものや、前歯と奥歯の長さに差があり前歯に咬合の負担が集中したことなどが挙げられます。